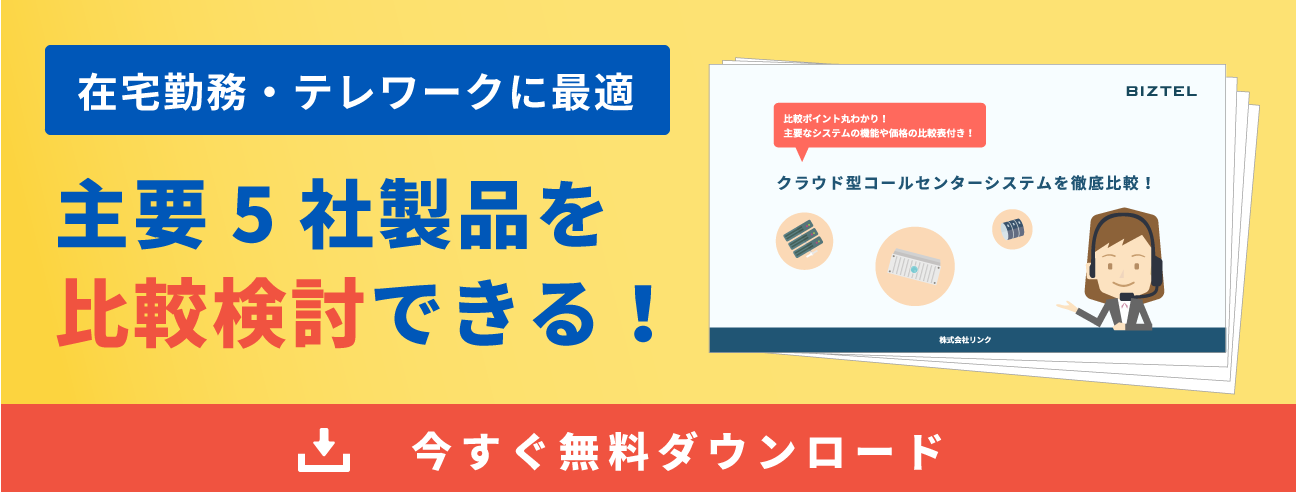【徹底解説】コンタクトセンターとは?概要・運営のポイント・期待される役割と効果まで丸わかり
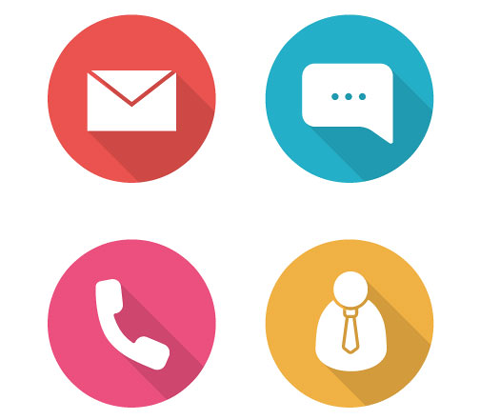
近年、製品やサービスそのものの質に加え、購入前〜購入後の丁寧なサポートを重視する消費者が増えています。いわば「顧客体験価値」がより重視される時代になったといって良いでしょう。
このような背景の中、「コンタクトセンター」の構築に着手する企業事例が増えています。
ではコンタクトセンターとはいったいどのような存在で、その構築には何が必要なのでしょうか。
この記事では、コンタクトセンターの基本や、コールセンターおよびカスタマーサポートとの違い、コンタクトセンター運営における課題と解決方法について解説します。
目次
1. コンタクトセンターとは?概要と特徴
従来のコールセンターは、主に顧客からの質問やクレームを電話で受ける場として存在していました。しかし、近年では問い合わせ手段は電話だけにとどまらず、メールやチャットなど多岐にわたります。
コンタクトセンターとは、このような様々なチャネルを通して送られてくる顧客からの問い合わせを、一括でサポートする仕組みのことを指します。対応方法が複数あること(マルチチャネル)や、良好な顧客体験価値を生み出す場であることが大きな特徴です。
もちろん、従来のコールセンターでも、顧客とのコミュニケーションを担っていました。
しかし今後は、様々なチャネルを通してコミュニケーションをとる必要があるため、コールセンターを補強しながら、コンタクトセンターの構築を目指す例が増えていくでしょう。
2. コンタクトセンターとコールセンターの違いとは
では、コンタクトセンターとコールセンターにはどのような違いがあるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
コールセンターの定義
日本コールセンター協会※によると、コールセンターとは「顧客や消費者のインバウンドやアウトバウンドの電話応対を行う拠点・窓口のこと」と定義されています。
日本コールセンター協会※によると、コールセンターとは「顧客や消費者のインバウンドやアウトバウンドの電話応対を行う拠点・窓口のこと」と定義されています。
インバウンドを行う担当者は(テレフォン)オペレーターと呼ばれ、商品の受注や問い合わせ・クレーム対応などを行うことが多いです。また、アウトバウンドの担当者は(テレフォン)アポインターとも呼ばれ、主にコールセンター側から顧客へ新商品・サービスの紹介などを行います。
※日本コールセンター協会
https://ccaj.or.jp/glossary.html
「対応するコミュニケーションチャネル」が異なる
コールセンターはその定義の通り、主に電話対応をメインとした組織として設置されるのが一般的です。
一方で、コンタクトセンターは上述の通り電話だけでなく、SNSやチャットなどの幅広いコミュニケーションチャネルを利用するため、多様なチャネルを統合し、一貫した顧客対応を実現できる仕組みを設ける必要があります。
「コストセンター」から「プロフィットセンター」への変化
従来、特にインバウンド型コールセンターは、利益の創出には結びつかない活動がメインであったため、コストセンター(支出が多く計上される部署)として見られやすい傾向にありました。
対して、様々なチャネルを通して良好な顧客体験価値を提供するコンタクトセンターは、結果として営業活動にも影響するため、戦略次第でプロフィットセンター(利益を生み出す組織)になる場合もあります。
複数チャネルにおける顧客情報の蓄積・収集や、見込み顧客への購買促進の実施によって満足度アップや新たな付加価値を生み出すことができるという点で、コールセンターとは異なるといえるでしょう。
3. コンタクトセンターとカスタマーサポートの違いとは
コンタクトセンターやコールセンターに類似するもう一つの概念として、カスタマーサポートが挙げられます。これらは混同されやすいものですが、以下のような違いがあります。
カスタマーサポートの定義
カスタマーサポートの目的は、電話や対面などのチャネルの種類を問わず、顧客をサポートすることです。
電話以外のチャネルにも対応しているケースが多く、その点ではコンタクトセンターとも共通しますが、特にアフターフォローなど「購入後における顧客の課題を解決する」役割を強く持つのがカスタマーサポートの特徴です。
カスタマーサポートの業務内容
カスタマーサポートの主な業務としては、商品・サービスの設定作業の支援や導入に関する教育・研修、トラブルシューティングやアフターメンテナンス、不良品・トラブルへの対応、そのほか問い合わせの受け付けなどが挙げられます。
顧客からの問い合わせは貴重な接点です。製品に対して抱いている想いや不満点などを吸い上げてスマートに解決し、満足度の向上を目指すことが求められます。
カスタマーサポートとは顧客接点や支援の姿勢が異なる
コンタクトセンターは、複数のチャネルを通して、企業側からも顧客とのコミュニケーションが活性化するように働きかけ、課題解決だけでなく、価値ある体験の創出を図っていく役割を担います。契約前〜成約〜契約後まで幅広い接点を持ち、購入や継続利用といった利益を生む顧客行動に結びつくことが多いです。
一方でカスタマーサポートは、主に製品やサービスの購入・契約をした後の支援を行います。顧客からの問い合わせに対応し、課題を解決するのが主な役割です。そのため、購入・契約前にコミュニケーションをとる機会が少なく、利益を生む活動と直接的に結びつくことも少ないでしょう。
以上の通り、コンタクトセンターはより能動的かつ企業発信型の側面を持つのに対し、カスタマーサポートは受動的で顧客発信型であるといえます。
4. なぜ今コンタクトセンターが重視されているのか?
コンタクトセンターが重視されるようになった背景には、ふたつの理由があります。
ひとつめは、「消費者の価値観の変化」です。これまで消費者は、購入するサービスや製品自体に価値を見出していると考えられていました。
しかし、最近ではサービスや製品そのものに加えて「購入したという体験」や「企業とのコミュニケーション」にも価値を見出す傾向が強いと考えられています。
つまり「顧客体験価値=カスタマーエクスペリエンス(CX)」が重要性を増しているのです。この顧客体験価値を担う場がコンタクトセンターです。
ふたつめは、顧客とのコミュニケーション手段が多様化していることです。スマートフォンやタブレットの普及で電話以外の通信手段が発達した今、顧客とのコミュニケーション手段は電話・Eメール・FAX・チャットなど多岐にわたります。これは「オムニチャネル化」と呼ばれています。
どのチャネルでも一定のサービスレベルの窓口を提供することで、顧客に安心や信頼を感じてもらいやすくなるといわれています。そのため、様々な対応手段を用いて良質なサービスを提供するコンタクトセンターの構築が求められているのです。
5. コンタクトセンターが果たす役割
期待される役割
このように重要さを増すコンタクトセンターは、「顧客との良好な関係を構築する」という役割を負っています。クレームや質問に対応するだけではなく、顧客体験価値を高め、エンゲージ(愛着)を抱いてもらうような対応を行うことで「ファン」を獲得できます。ファン層の形成は、売り上げの安定化だけではなく、より良いサービス・製品の開発にも貢献するでしょう。
さらに、「サービスレベルの均一化された応対」という役割も期待されています。応対品質は、オペレーターのスキルや経験に依存しがちです。しかし、属人的なスキルや経験によって応対品質が上下する仕組みでは、オムニチャネル化への対応として不十分だといえます。
様々なITシステムを活用してコンタクトセンターを構築することにより、誰が、いつ、どういった手段で接触しても、同じようなサービスを受けられる、といった効果が期待できるでしょう。
加えて、「他部門との連携」もコンタクトセンターに課せられる業務内容のひとつといえます。顧客から吸い上げた情報を開発部門やマーケティング部門へ展開できれば、サービスの企画や製品開発に役立つほか、マーケティングの効果を高めることができるでしょう。
このようにコンタクトセンターは、企業の持続的な成長に寄与する存在として期待されているのです。
顧客満足度の高いコンタクトセンターづくりに必要なこととは?
顧客がサービスに触れ、問い合わせが発生してからコミュニケーションが終わるまで、一貫して「顧客が満足する品質の応対」を「チャネルを問わず」提供できることがコンタクトセンターの理想形です。
上述した通り、顧客とのコミュニケーション手段が多様化するなかで、コンタクトセンターには電話だけではなく、メールやチャットなど様々な経路を介した顧客への対応が必要とされます。こうした複数の窓口を持つ場合、同一の顧客が別々の経路で問い合わせたり、各窓口から別の窓口への引き継ぎが発生したりすることも珍しくありません。
そのためコンタクトセンターは、すべてのチャネルで顧客に不快・不満を抱かせないサービスレベルを維持することが重要です。
どのチャネルでも一定の応対品質が維持できれば、顧客は時間や場所にとらわれず、選択しやすい手段を用いてサービスにアクセスできます。ストレスのない体験をあらゆる経路において提供できれば、顧客ロイヤルティの向上につながるでしょう。
このようにコンタクトセンターづくりには、問い合わせ経路を複数用意するだけではなく、それらのチャネルを通して総合的にどのようなCXを提供するか、という視点が欠かせません。
現代のビジネスシーンでは顧客体験価値の向上が重要視されていますが、コンタクトセンターにおいてもその一翼として顧客により良い体験を提供することが求められます。
そのためには、顧客にストレスを感じさせない問い合わせ導線の設計や、オペレーター間でのスムーズな情報連携・エスカレーション体制の整備も重要となるでしょう。
6. コンタクトセンター運営のポイント
ここまで、コンタクトセンターの概要や役割、求められていることについて解説をしてきました。
ここではより具体的に、コンタクトセンターを効率的に運営するためのポイントについて解説します。
応対品質の向上
チャネルを問わず、良好な顧客体験を提供することを目的とするコンタクトセンターにおいて、応対品質の向上は最も重要といえるでしょう。オペレーターの対応がスムーズであるほど、顧客へ与える印象も良くなります。
応対品質の向上策としては、過去の問い合わせ内容や顧客情報をCRMに登録し、チャネル間での切れ目のない対応を実現したり、属人化しがちな知識やノウハウを共有して標準化を図ったりする取り組みなどがあげられます。
また、電話やチャット・SNSといった複数接点の情報を統合するオムニチャネル化も応対品質の向上に繋がるでしょう。
対応時間の短縮化・業務の効率化
コンタクトセンターの生産性を向上させるためには、対応時間の短縮化、業務の効率化が必要です。たとえば、問い合わせの多い内容を整理した上で、チャットボットなどを導入してFAQの参照を促す導線を作り、一次問い合わせの切り分けを実施することなどが考えられるでしょう。
顧客の自己解決を促すことで、入電数を減らすことにつながります。また、CTIなどが提供している入電を分配する機能を用い、オペレーターの業務スキルに合わせて適切に振り分けるといった対策も効果的です。
売上向上への貢献
重要な顧客接点であるコンタクトセンターには、売上向上への貢献が求められます。音声認識AIを活用した通話内容のリアルタイム解析によってオペレーターを支援したり、商品・サービスの提案力向上を図ったりする取り組みが有効です。
また、適切な顧客対応を続けていくことにより、ロイヤルティ向上やファンの獲得などを目指していくといった、長期的な視点での活動も重要です。
離職率の抑制
コールセンターやコンタクトセンターでは、顧客の窓口対応を行うオペレーターの離職率の高さが業界全体の課題となっています。オペレーターの新規採用に苦慮している企業は多く、仮に採用できたとしても改めて教育を行う必要があるため、コストも時間もかかってしまいます。
オペレーターの離職率を下げるためには、業務にかかる負荷やストレスを軽減するなどして働きやすい環境を整えることが重要です。
たとえば通話内容の要約システムを利用し、応対履歴の登録を自動で行ったり、AIによる感情分析を用いてオペレーターのストレスケアやモチベーション維持を実施したりするといった対策が考えられます。
オペレーターの教育
コンタクトセンターで対応を受ける顧客の満足度は、担当したオペレーターの力量に大きく左右されます。よって、オペレーターの教育はコンタクトセンターの品質向上やクレーム防止の観点からも重要です。
近年ではコロナ禍の影響で集合研修が難しい状況であるため、クラウド型の教育管理システムの活用も検討するとよいでしょう。
また、実務を通してオペレーターの対応力を向上していくことも大切です。コールセンターシステムによっては、SVから通話中のオペレーターに音声で指示が出せるモニタリング・ささやき機能が備わっているものもあり、オペレーターの教育・指導に活用できます。
7. コンタクトセンターにおける課題を解決するための方法
コンタクトセンターにおける課題を解決し、効果的に運営をしていくためには、具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか。以下では代表的な手法について解説します。
CTIとCRMの連携
コンタクトセンターにおいて顧客との良好な関係を構築していくには、顧客への適切かつ迅速な応対が必要です。そのためには、「誰から電話がかかってきたのか」「その顧客とはこれまでにどのようなやり取りをしたのか」などの情報がすぐに把握できるようにすべきでしょう。
これを実現するのが、CTIと顧客管理システム(CRM)の連携です。顧客情報や応対履歴は一般的にCRMで管理されますが、CRMとCTIの連携によって、入電のあった電話番号と顧客情報を紐づけ、オペレーターが確認できるようになります。
これにより、顧客対応の効率化はもちろんのこと、スムーズな応対による顧客ロイヤルティの向上や、問い合わせ履歴を活用した顧客への提案力向上などの効果も期待できます。
チャットボットの利用
AI技術を活用したチャットボットを導入することで、テキストベースでの顧客対応が自動でできるようになり、入電数の削減が見込めます。リソース不足や問い合わせの業務過多に悩むコンタクトセンターにおいては、大きなメリットといえるでしょう。
特に若年層を中心に、電話よりもテキストでのやり取りを好み、チャットボットがあればそちらを利用したいと考える消費者も増えています。
ただし、チャットボットは技術的な制約があり、定型的な回答が中心となる点には注意が必要です。顧客の求める回答ができない場合はオペレーターにエスカレーションできるようにするなど、チャットボットが対応できない範囲をフォローする仕組みをつくっておくことがポイントです。
FAQの充実
簡易的な内容の問い合わせ対応により業務が圧迫されている場合は、自社のWebサイトなどにFAQを作成して顧客に自己解決を促す仕組みを作ることが有効です。
チャットボットと同様に入電数を削減できるため、業務の効率化につながる可能性があります。過去の問い合わせ内容から顧客が疑問を抱きやすいポイントを洗い出し、あらかじめ回答を用意しておきましょう。
また、オペレーターもFAQを参照できるようにすることで、応対品質の向上や対応時間の短縮効果も期待できます。他にも、FAQを拡充し、チャットボットによってそれらに誘導する導線を作ることで、疑問や課題についてユーザー自身が解決しやすくなります。一次解決の効率が向上するという点で、FAQの定期的な見直し・拡充は重要といえるでしょう。
ただし、FAQでは解決できないケースももちろんあるため、コンタクトセンターへの誘導も忘れてはいけません。
運営代行・アウトソーシングの利用
特に繁忙期においては、人員不足の影響が深刻化するケースがあります。そういった場合は、運営全般もしくは架電・受電対応など一部の業務をアウトソーシングすることで、人員の需要変動に対応しやすくなります。
自社でオペレーターを採用する必要がないため、コストや時間が削減できるほか、自社内での教育にかかる手間も減らせます。
ただし、アウトソーサーが自社と別の拠点で対応を行うケースでは、オペレーターに直接指導することが難しいです。そのため、回答や説明の仕方などについて、スピーディーな改善ができない点に注意が必要です。
8. コンタクトセンター運営に役立つサービス
以下では、コンタクトセンター運営に有効なサービスを紹介します。
業務効率化ならCTIシステム
CTI(Computer Telephony Integration)とは、コンピューターと電話を統合するシステムです。PBX・電話端末などとPC・外部システムを連携して、業務を効率化する付加機能を提供します。コンタクトセンター運営において、CTIの導入は必須といえるでしょう。
CTIシステムの代表的なサービスとして、BIZTELコールセンターが挙げられます。
BIZTELコールセンターは、クラウド型のCTIとして2,000社以上に導入されています。規模に関わらずどのようなコールセンターにもマッチでき、最短5営業日という短期間での導入が可能です。
問い合わせチャネルの増設ならチャットボット・FAQ
チャットボットやFAQは、顧客とのコミュニケーションチャネルを増やすのに有効です。代表的なサービスとしては、FastAnswer2やDEC Supportが挙げられます。
FastAnswer2は、「よくあるご質問」などの外部公開用FAQと、オペレーターが顧客対応時に参照する内部用FAQの両方を管理できる、テクマトリックス社のFAQナレッジシステムです。コンタクトセンターに寄せられる顧客の声をナレッジとして蓄積し、参照しやすいFAQとして有効活用できます。
またDEC Supportは、トランスコスモス社が提供するチャットボットサービスです。上述したBIZTELコールセンターと連携することで、顧客がチャットボットとやり取りした内容を、エスカレーションを受けたオペレーターに表示できます。
これにより、顧客はチャットボットに回答した内容をもう一度オペレーターに伝える必要がなくなり、効率化や応対品質向上を実現できるでしょう。
リソース不足なら運営代行・アウトソーシング
人材不足・業務過多や繁忙期のリソース不足解消に有効なのが、運営代行やアウトソーシングです。BIZTELでは、コンタクトセンター業務の委託サービスである「アウトソーシングオプション」を提供しています。繁忙期や特定の時間帯などの部分的な業務委託に加え、フルアウトソースの利用も可能です。
応対品質向上・教育力アップなら教育管理サービス
応対品質を向上させるには、オペレーターへの教育が欠かせません。一方で、社内で教育を行うためには、管理者や熟練者クラスのリソースが必要となり、負荷も高くなります。
そこで有効なのが、クラウド型の教育管理サービスであるBIZTEL shouinです。BIZTEL shouinでは、応対マナーやクレーム対応などに関するプロ講師による研修動画がプリセットされているため、すぐに研修をスタートできます。また、オリジナルコンテンツをアップロードして利用することも可能です。
さらに、研修受講状況の確認やクイズによる理解度のチェックによって、効率よく教育を進められます。クイズの結果やスキル定着の状況が個人別に把握できるため、オペレーターの知識・応対品質の平準化が図れるメリットもあります。
9. まとめ
このようにコンタクトセンターは、顧客体験価値を高める場として期待されています。コンタクトセンターの構築で、ファン層の形成、サービスレベルの均一化、他部門との連携を強化できれば、企業の持続的な成長が実現しやすくなります。日本国内ではまだ浸透しきっていないコンタクトセンターだからこそ、他社に先んじて導入できれば、その効果を実感しやすいのではないでしょうか。
また、コンタクトセンターへの構築には、コールセンターシステムをはじめとしたITシステムの活用が重要です。コンタクトセンターを構築するシステムについて不明点があれば、サービス提供会社に問い合わせてみましょう。
*「コンタクトセンター」関連のおすすめ記事














 資料ダウンロード
資料ダウンロード